|
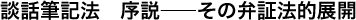
談話筆記法の理論的構築にあたり、談話(話すこと)と筆記(書くこと)の二元論を「一つ」にする。
そして、談話筆記に携わる談話筆記者(dictation)、録音談話筆記者、録音談話書記(トランスクライバー)の理論的立脚点をデッサンする。
この新しい視座から、本稿の理論的支柱である貴重な研究の資産といえる元東北大学教授 文学博士 佐藤喜代治先生のコンテンツを新しく解釈し直し、再構成(新しく組み合わせる)して新しいコンテンツをつくる。異なった働きの組み合わせで新しい働きを生み出す、それは全く新しい価値をつくり出すのだ。
談話筆記法は何からつくられているのか。
新領域 新しい形式の誕生――姿として現れる瞬間。
「談話筆記」をわが国国語辞典の新しいことばとして獲得していく道であればいい、国語の一分野として認知されるよう望んでいる。
A. 現代自然音声言語(話しことば)の現実的・歴史的側面
voice-transcriptionをDNA(デオキシリボ核酸)になぞって、それを物象化(科学的連想)して考えてみると、発現(expression)して初めて意味をもつという。発現には転写(transcription)と翻訳(translation)の二段階があるらしい。
voice-transcriptionは第一稿・草稿の意味にしかすぎない。DNAだけでは情報の塊(プログラムなど)としてしか存在意義はないが、状況に応じて必要なものを選び、それを適当なかたち(from: 姿として現れ出る=outwardされる=RNAを経てタンパク質として)としてoutputすることで意味をもつようになる。この転写後の過程をスプライシングsplicing(もともと「フィルムやテープを編集する」「より継ぎをする」などの意味)と呼ぶらしい。成文や作品にもなる。(ホームページ「ごあいさつ」より)
小社においてメディアにパッケージィングされた、話しことばである録音談話著作物が毎月700時間を越えて、新聞社、出版社等から依頼される。クライアントのDNAである「音声データの構造体」を転写(transcription)している。
それらはディクテート(談話筆記)、インタビュー、対談、鼎談、座談会、講演、会議、その他などである。
カセットテープ、MD、CD−R、そして電子メールその他で音声ファイルとして送られてくる。
新聞社や出版社は転写に高いコストをかけている。高精度の転写には価値があり、そしてコンテンツの制作にはじめて第一稿(転写原稿)としての意味をもつ。
転写精度が高いほど価値がある。転写精度が低いと劣悪である。またコスト、短納期もカギになる。そして、転写精度は知識労働者の知力に依存している。コスト高になる理由である。
音声認識装置が道具として適用できないのは、転写精度が低いからである。
情報には主に視覚情報と聴覚情報など五感覚情報がある。
人は「目で見て、耳で聞き、肌で触って、匂いを感じ、そして舌で味わって」感じる。テキスト原稿は、挑戦できるだろうか。
マスコミの新聞社、出版社の取材やインタビューなど談話を表記ことば(文字言語)へ転写するビジネスは、かつてのニュービジネスからスタンダードなビジネスへ変化(進化)した。
多様なメディアで生産される人間の談話(音声言語)は、メディアミックス化され、表記文字を中心として転写して電子デジタルテキストのコンテンツ創造の時代を迎えて久しい。多様なメディアの土台は、今でも電子デジタルテキストから発信する。
コンテンツ創造の始まりは、「はじめにことばありき」である。ことばには音声言語と文字言語があり、「○○はこのように語った」と述べた。音声言語(談話)と文字言語(筆記)との一致である。ぼくたちは人間として本源的な「一致」の美しさを求めていく。
正しく正確に広く後世に伝えなければならない。聖書においても仏典においても、ことばは正確・忠実で真実を伝えることばでなければならないだろう。
ことばは教えを広めることから、マス・コミュニケーションがスタートしたと言ってもいいだろう。原始的な口コミで広がっていったのかもしれない。人間社会史のコミュニケーションは伝えあったり、教えの精確な転写(写経、清書:manuscript)と印刷から広がっていったのだろう。
テレビやBSラジオ放送その他、有線放送、インターネット放送(ポッドキャスティング)では、未編集の自然談話放送が日常放送されている。
テレビ局の創世期、昭和30年代の春4月になると、学園では地方訛りの話しことばが飛び交っていた。明治時代からこんにちまで口語から敬語が徐々に失われていったのだろう。ぼくたちは第一稿(transcription)で「話されたこと(談話)」とそれを「書くこと(筆記)」の一致を厳しく守っている。
佐藤喜代治博士は、「話すこと」について「書くこと」の働きの比較の中で違いを描き、話すことの特色を語っている。
落語家の日本語は代々受け継がれてきたと思われる。
明治以前と明治以後の近代日本語正書法(句読点など)の萌芽がみられる。
私事で恐縮だが、母から聞いたことだが、私の祖母は昭和の初期、毎日午後、自宅で新聞小説を近所のおんな友だちに読み聞かせていたらしい。朝の連続テレビ小説を観て楽しむように、毎日のおしゃべりが楽しみだっただろう。祖父は昭和の20年代、同じように講談本をじいさま友だちに読み聞かせて楽しんだ。昔は、「読み、書き、ソロバン」のように権威主義的に「お触れ」を出して、書くこと、読むこと、話すこと、聞くこと、の中にいた。
民主社会では始めに自由に「話す」があり、ワールドカップサッカーも自由な社会で健全な愛国心が自然とあふれ出て、共感が周りの友との「話し合い」の輪へと広がっていく。話すこと、聞くこと、書くこと、読むことの順番につながっていくのではないか。
人々の話し合いから自警団がつくられて民族国家(書く)へと歩む。
また講談と浪曲の文字化に当時は速記者が腕をふるったと思われる。
祖父は江戸末期の慶応元年生まれであった。当時から日本語は息づいて生きている。
わたしの記憶でも日常の会話は社会的に代々受け継がれてきたと思われる。野性的な本能であれ、社会的な理性であれ、ことばは同化模倣の真髄である。ことばは、民族の表現だ。訛りは6、7歳頃で同化模倣される。
戦後テレビなどの全国放送が国民の話しことばの標準化(東京アクセント・大阪アクセント?)を進めた。
考えてみると、人が集まるところでの意思の疎通には標準化された話しことばと、表記文字の伝えやすい表現を工夫してきたといってもいい。
ある関係当局から「文書」が郵送されてきた。
どういうことを言っているのか分かりにくく、出向いて話を聞きたいと思った。
こういう経験はみなさんも時々あると思う。
「書かれた文書」の意味がはっきりと分からないのである。話を聞いて理解を深める。不安を取り除く。
小・中・高・大学と「知識の構造」を教え説明するには、口頭で話して教え聞かせることも必要だ。電子機器の操作マニュアルはどうだろうか。
16世紀のイギリスでは書かれたものよりも口頭で言われたことを人々は信じた。
習慣法が出てきたのもこうした歴史の背景があったのだろう。書かれたものは信用できなかった。事実と違うことは「ウソ」をついたと言った。欧米ではこのように広く思い込まれていた。
ジェントルマンは言行一致して、野蛮人は「ウソ」をつくといわれていた。
契約の思想は訴訟や裁判の思想でもある。訴訟社会は何を生み出したのだろうか。
話すことの意味は深い。話し合いは共同体や社会の環境を変える。
テレビや新聞、出版物などこんにちではインターネットやブログなどの多様なメディアが、コミュニケーションの生産的な道具となった。多様なメディアの発達とともに、情報化社会へ突入した。ケータイ電話は新しいメディアとなり「話す」ことは楽しい。この話すことが第一番(第一義的)の庶民文化となった。情報化社会で自分の元気印の「存在の証明」でもある。
ぼくたちはこうして情報化社会の良質なコンテンツ生産に携わっている。
ヨーロッパにおいては小社ホームページ『ヨーロッパにおける速記者の歴史と異なったトランスクライバーの歴史(スケッチ)』を参照されたい。
現実的歴史的本質(1,2,3で構成)
1. 現実的歴史的本質(第1分析)
2. 理論的本質(第2分析)
3. 実践的本質(第3分析)
B.文字言語(筆記)の理論的側面
──録音再生原稿のつくり方とその理論的展開
話すことの理論的側面(本質)
書くことの理論的側面(本質)
日本語による話しことばは、その人の人格の価値観を国語によって表現する。
うまい表現とか、下手な表現とかではなく、それは生きている思想と価値観の叫びなのだ。
ぼくたちは仕事として著者の談話を現す過程で、己を対象化し、客観化して、日本語の日本語による日本語の表現法を通して自分を入り込めて実現(表記・共感)しようとする。
広場に立つ彫刻を見ると足元が見えない。立つ足場がないのだ。
ぼくたちは自身の理論的立脚の場を生み出していこうではないか。
ぼくたちはどこにどのように立つのか。
元東北大学教授 文学博士 佐藤喜代治著『国語表現法』(朝倉書店)をテキストとする。
この著書は当時、東北大学で学生の教科書として採用されていたものと思われる。
筆記の理論については小社ホームページで断片的に述べている。参考にされたい。
筆記理論の構造・構成は以下のようになっている。
理論的本質(1,2,3で構成)
1. 現実的歴史的本質(第4分析)
2. 理論的本質(第5分析)
3. 実践的本質(第6分析)
 『国語表現法』 『国語表現法』
東北大学名誉教授 文学博士 佐藤喜代治 編 (朝倉書店、昭和47年)
執筆者
佐藤 喜代治(東北大学教授・文学博士)
蒲生 芳郎(宮城学院女子大学助教授)
加藤 正信(東北大学助教授)
前田 富祺(東北大学助教授)
目次
1. 総説 ことばの力
2. 話すこと
一 話しことばの特色
二 発声と発音
1 発声と発音
2 母音・子音・音節・文節
3 アクセント・イントネーション・プロミネンス
三 話し方
1 話し方
2 敬語
四 話すことの実際
1 会話
2 会議
3 一対多の場合
3. 書くこと
一 文字と文章
1 文字・表記法・校正
(1 文字・表記法・校正)日本語「現代(戦後)正書法」が成立する背景を学ぶ
文字の種類
日本で使われている文字には、漢字・片かな・平がな・ローマ字などがある。漢字だけを使って表現することは、まれに新聞の案内欄などに見られるが、現在では一般的ではない。ローマ字だけで表現することも特別な場合にはあり、また国語をローマ字で表記すべきだという主張もあるが、これも一般的になってはいない。片かなを使って国語を書き表わそうとする運動もある。片かなはかなタイプにも用いられており、最近は手紙などのあて名に使われることがある。電報は片かなで書くものの一つである。しかし、片かなだけだと誤解の恐れのある場合も多く、複雑な内容のことをできるだけ正確に伝えることは困難である。分かち書きをどのようにするか、同音語をどのように言い換えるかについての整理がつかないという事情がある。このことは、平がなだけで書き表わす場合も同じことである。
一般には、漢字とかなとを併用している。漢字とかなとを混ぜた文をかな交じり文というが、これは厳密に分ければ、漢字と片かなとを混ぜた漢字片かな交じり文と、漢字と平がなとを混ぜた漢字平がな交じり文とになる。このうち漢字片かな交じり文は以前はかなり広く使われていたが、現在は一般的でない。したがって、以下では、漢字平がな交じり文を中心として述べることにする。
文字の使い方
文字の使い方では、まず第一に漢字の使い方が問題となる。漢字の使用は時代とともに少なくなってきている。この傾向に従って、昭和二十一年に「当用漢字表」が政府から発表された。「当用漢字表」は、ふつう一般に用いられる漢字を一千八百五十字に制限しようとするものである。なお、昭和二十六年には、人名に用いてさしつかえのない漢字が発表されている。これを「人名用漢字別表」という。また昭和二十九年には「当用漢字補正資料」が発表された。これは「当用漢字表」から削るべき字と、「当用漢字表」に加えるべき字とを決めたものである。ただ、人名や地名では当用漢字以外のものを使わざるをえない。また、学術用語など、他に言い換えることのできない場合もある。
昭和二十三年には、「当用漢字音訓表」が発表され、現代国語を書き表わすために、日常使用する漢字の音訓の範囲が定められた。これによって、漢字の数ばかりでなく、その読み方も制約されたわけである。そのために、同音の漢字による書き換えとか別の語に言い換えるとかいう必要も起こってきた。
昭和二十四年には、「当用漢字字体表」が発表されている。これには許容される形もしるされているが、「■*1」「■*2」「仂」など、現在通用している字体でも認められていないものがあるので注意を要する。
昭和三十四年には「送りがなのつけ方」が発表された。これでは活用語尾の部分を送るのが原則となっているが、活用語から転じた名詞の場合に、たとえば「終(わ)り」「代(わ)り」のように、活用語尾の部分を省いてもよいものがあり、許容される事項があるので注意を要する。
昭和二十一年には「現代かなづかい」が発表されている。現代かなづかいは現代語の発音に従って発音どおりに書くことが原則である。しかし、助詞の「は」「へ」「を」は発音によるものではない。また「もとづく」「はなぢ」など語源意識の残っている場合や、「ちぢむ」「つづみ」など同音の連呼で生じた場合は、歴史的かなづかいのまま、「ぢ」「づ」を使うのである。オ段の長音は「う」をつけて示すが、「おおきい」「とおい」など例外となるものがいくつかある。エ段の長音は「ええ」「ねえさん」のように、「え」をつけて書くことになっているが、現代語で一般にエ段の長音として発音される「映画」「経済」などは「えいが」「けいざい」のように「い」と書くことになっている。これらによってもわかるように、現代かなづかいは文字どおりの発音かなづかいなのではなく表音を原則とした一種の正書法なのである。したがって、英語のつづりを覚える時のように原則と例外とを規則として覚えこみ、あとは実際の使用にあたって疑問のあるものは調べなおすことが必要である。
特別な考えがないかぎり、なるべく当用漢字の範囲内で音訓表に示された音訓に従って漢字を使い、送りがなは「送りがなのつけ方」に従うこととし、現代かなづかいで文章を書くのがよい。当用漢字・現代かなづかいなどは、大抵の国語辞書の巻末につけられているので、わからない場合には確認してみる必要がある。また、最近の国語辞書では、見出しの漢字が当用漢字内の字かどうか、送りがなはどうなるかなどをしるしているものが多い。文章を書く時はいつも手元に国語辞書を置いておいて大儀がらずに引いてみるべきである。慣れると次第に引かなくともわかるようになってくる。
■*1は、みみへんにム、■*2はにちへんに玉
漢字とかなとの使いわけ
読みやすくわかりやすい文章を書くことが大事であるから、漢字とかなとが適度に混じっていることが必要である。むずかしい漢字が多すぎると読むのに時間がかかる。また、かながあまり多すぎると、どこで切ってよいかがわかりにくいために、かえって読むのに不便である。しかしどの程度に漢字とかなを混ぜるかについては一定の決まりがあるわけではないので、各人の文体に合った表現をとるような心がけが必要である。また、その文章の目的・内容によって変わってくるのも自然であろう。どちらにしても、同一文章内で不統一にならないように注意すべきである。
漢字は「当用漢字表」、「当用漢字音訓表」によって用いるべきことはすでに述べたとおりである。これにはずれるものの使用を避けるためには、そのことばをかな書きにすることも一つの方法である。動植物の名前は、「ねずみ」「つばき」などかな書きにするとよい。もちろん、「犬」「桜」など「当用漢字表」にあるものは漢字で書いてよい。和語・漢語で日常使い慣れ、聞いてわかりやすいものは「さかのぼる」「あいさつ」などのようにかな書きにすることができる。語によっては、「編輯」を「編集」、「碇泊」を「停泊」などと同音の字に書き換えることによって当用漢字以外の漢字の使用を避けることができる。また、「斡旋」を「世話」、「抹消する」を「消す」など言いかえるのも一つの方法である。学術用語など言い換えの困難なものは、「昆虫」を「こん虫」、「語彙」を「語い」など当用漢字からはずれた字だけをかなにすることもある。
地名・人名や、学術用語、詩歌などでどうしても使いたい語は、当用漢字外のものを使わざるをえないこともある。かな書きにするとどうも意味がわかりにくいということもあるし、「語い」のような表記は見た感じが悪いということもある。その時は、「語彙」「時雨」のようにふりがな(ルビ)をつけて、読めない人のないようにすることも考えられる。ただ、ふりがなが多いと印刷に面倒なので、あまり多くない方がよい。「五月雨(さみだれ)」のように、かっこに入れて読み方を示すのも一つの方法である。
一般の文章は読みやすくわかりやすいということが大切であるから、漢字があまり多すぎないのがよい。代名詞・連体詞・接続詞・助動詞・助詞はなるべくかな書きにしたほうがよい。「所」「物」などが形式名詞として使われる場合もかなで書く。「居る」「見る」なども、補助動詞的な使い方の場合はかなにする。あて字も使わないようにして、かなで書くことにしたい。
外国語・外国の地名・人名、その他、いわゆる外来語は片かな書きにする。ただし、中国の地名・人名は漢字で書く。擬声語なども読みやすくするために片かなで書くことがある。
音符の使い方
濁点・半濁点 古くは濁点・半濁点をつけないのが普通であったが、現在は平がな・片かなにかかわらず濁点・半濁点を正確につけていかねばならない。特に外来語の場合、「ブロマイド」を「プロマイド」、「ビーチ・パラソル」を「ピーチ・パラソル」など間違ったものが見られるので注意を要する。年配の者は「アパート」を「アバート」などパ行をバ行に間違うことがある。また、方言によって清濁の違うものもある。
促音符 明治・大正のころまでのものでは、「つ」「ツ」を大きい字のままで使っていることが多かった。しかし、これではタ行の「つ」「ツ」との区別がつかないので、右下に小書きにする必要がある。横書きの場合も同様である。
撥音符 明治のころまでは「む」を使うこともあったが、現在「ん」「ン」を使うことになっている。
長音符 現在、母音をつけて長音を示すことはかなづかいのところで述べたとおりである。外来語を片かなで記す場合には「ー」の記号を使う。
拗 音 平がな文では「ゃ」「ゅ」「ょ」のかなを、片かな文では「ャ」「ュ」「ョ」のかなを右下に小書きにつけて示す。横書きの時に右上につける者があるが、横書きの場合も右下に小書きにつけて示すべきである。
反覆符号 反覆符号は繰り返し符号、または、おどり字といわれている。「ゝ」(一字おどり、一つ点)、「■■」(二字おどり、くの字点)、「々」(漢字おどり、同の字点)、「■」(二の字点)がある。現在、かなの一字の繰り返しの場合は「ゝ」、かな二字以上の繰り返しの場合は「■■」、漢字の場合は「々」を使っている。たとえば「あゝ」、「いよ■■」、「時々」などのように書くが、なるべく使わないほうがよい。特に「■■」はどこから繰り返すのか、あいまいなことがあるから、かなを繰り返して書くとよい。なお、「たゞ」、「かえす■■」のように濁点をつけて使うこともある。「とじ■■」、「かえす■■」などのように、二字おどりの場合は連濁を示すものであることは注意を要する。横書きの場合は反覆符号を使わないほうがよい。時に「■■」を横に書いたりするものが見られるが、これは避けるべきである。「■■」を用いるときは、「く」のかなと間違いやすいので、二字分をとって書くようにする。
■は、特殊記号のため表示できません。こちらを参照して下さい。
句読点の使い方
句点(。 ) 文と文との切れ目を示すためにつける。題目や標語の場合はつける必要がない。会話の文の引用の場合に、最後の文の終わりは句点と 」が同じますめにはいるので省く人もいるが、これもつけておいたほうがよい。
読点(、 ) これは文の中で息の切れ目となるようなところにつける。読点をつける場所は人によって異なり、一定していない。読点は多すぎても少なすぎても読みにくい。意味をはっきりさせ、修飾句と被修飾句とがどういうふうにかかっているかを示すために、読点がつけられることもある。対等の語句が一文をなす場合とか、条件句などの場合は、読点をつけるのが普通である。このほか、文の主題となる語句、感動詞、接続詞の後でもつけることが多い。ともかく、わかりやすく正確な表現ということで読点をつけるのがよい。
なかぐろ(・) なか点ともいう。同類の物の名を列挙する時に使う。外国語のくぎり、略号のくぎりなどにつけることもある。
傍点(・・・) 脇点ともいう。「■■■」(圏点)を使うこともある。特に注意すべき語句がある場合に、その字の右側に一つずつうつ。あまり多いとかえって効果が薄くなる。
■は、特殊記号のため表示できません。こちらを参照して下さい。
かぎかっこ(「 」) 引用文、引用語句を示したり、会話であることを示したりする。ある語句を特にきわだたせたい時に使うこともある。
二重かぎ(『 』) 引用文中にさらに引用文が含まれている場合、会話の中で何かを引用している場合に使う。書名などの引用にかぎかっこの代りにこれを使う人もあるが、書名を引用文と区別する必要のある場合などは便利であろう。
クォーテーション・マーク( “ ”) 横書きの場合にかぎかっこの代りに用いられる。縦書きでもこれの代りに「■■」(ダブル・ミニット)を使うことがある。
■は、特殊記号のため表示できません。こちらを参照して下さい。
ピリオド( . ) 横書きの場合に句点の代りに用いる。もちろん、横書きでもピリオドを使わず。句点を用いてもよい。
コンマ( , ) 横書きの場合に読点の代りに用いる。
かっこ 一般には丸かっこ( )が用いられる。読み方を示したり、注釈や説明を補う場合に使う。説明でもあまり長くなる場合は丸かっこを使わず独立した文にすべきである。このほか、二重かっこ■■、角かっこ[ ]、袖がっこ〔 〕、すみつきパーレン【 】などがあるが、多く用いないほうがよい。山パーレン〈 〉、ギュメ《 》など、フランス風の引用符を用いる人もある。
■は、特殊記号のため表示できません。こちらを参照して下さい。
ダッシュ(?) 挿入句を示したり、注記、説明などに用いる。
点線(……) 会話などを中略する時に用いる。対話の中で無言ではあるが、間のある状態をも示す。
つなぎ(−) ハイフンともいう。外国語の切れ目を示す。「=」を用いることもある。
疑問符(?) 疑問の気持や疑問のイントネーションを示す。日本語では文末が「か」になることなどによって疑問であることがわかるから、あまり用いないほうがよい。まして強い疑問といっても、「??」などと疑問符を重ねることは避けるべきである。
感嘆符(!) 感嘆の気持を表わす時に用いる。これも疑問符と同じで、頻用すると品位がなくなる。「!!」「?!」などは使わないほうがよい。
米じるし(※) 傍注・頭注などの指示に用いる。
アステリスク(*) 米じるしと同じである。特に横書きの場合に用いられる。
傍線(─) 傍点と同じで特に注意すべき語句の右側につける。ある程度長い部分の場合は傍線のほうが傍点よりわかりやすい。横書きの場合はアンダーラインとよび、語句の下に引く。
原稿用紙の書き方
原稿用紙に文章を書く時には、必ず題をつけることにしたい。その題の長さや副題のあるなしによっても違うが、数行とって余裕を持たせて題を書く。できれば、上下・前後にある程度のスペースがあるほうがよい。なお、かぎかっこは引用の場合につけるのであるから、自分のつけた題をかっこに包む必要はない。もちろん題の中で他の本を引用したりする場合は、その書名をかっこに包まねばならない。原稿の枚数が多くなった時は、とじて表紙をつけ、表紙にも題を書くのがていねいである。原稿の枚数があまり多くない時は、原稿に題を書くだけで、表紙をつけなくともよい。この場合も原稿がバラバラにならないようにこより・糸などでとじておくべきである。原稿には必ず氏名を書くことも忘れないように。必要があれば、所属(学部・学年など)も書く。この場合は、所属・氏名は題の左側に題の高さよりも下げて書く。
原稿用紙は一字を一ますに入れて書く。草体でくずしてあっては困る。句点・読点・中点・かっこ類・疑問符・感嘆符などは、一字分とるのがよい。点線、くの字点などは二字分とって書く。行頭に句点・読点などがあると、読む人が前の行から続くものと思いやすいためにペースが乱れるので、行頭には句読点をつけないのが習慣である。そのために前の行の一番下の文字と同じますに句読点をつけたり、その文字の下の欄外につけたりする。ただ、このようにするとそのます目にいくつもの符号を入れたりすることも起こりうるから、その場合は表現を変えて調節したほうがよい。印刷される原稿用紙の場合は、原稿で行頭になっていても活字に組んでみて行頭になるとは限らない。したがって、行頭に符号が来てもかまわないが、活字で組まれて行頭にある場合は、校正の際に前の行の下に移すように訂正する。活字の間をつめたりして直してくれるはずである。
文章は適当な段落に分ける必要がある。そして、別の段落が始まる時に改行し、始めを一字下げにする。文章の書き出しの部分も一字下げにする。短い引用の場合はかぎかっこにくくって引用してもよいが、かなり長い文を引用する時は改行したほうがよい。この場合は引用文全体を一字下げにする。この場合も引用文の中でさらに改行することもありうるので、段落の始めはさらに一字下げにしておいたほうがよい。このほか、個条書きの部分も一字下げにしておいたほうがよい。会話の引用もかぎかっこでくくって改行したほうがよい。改行した引用、会話などに続く文は改行する。この場合、助詞の「と」で始まる場合は一字下げにする必要がないが、その他の場合は一字下げにしておく。
漢数字は縦書きに、算用数字は横書きに用いるのを原則とする。縦書きでも章、節の順序を示す場合は、算用数字を用いることがあるし、横書きでも「九州」「一時的」などの固有名詞、熟語は漢数字を用いる。漢数字は「千九百七十年」のように「十」や「百」を入れて示すのが正式であるが、「一九七〇年」のように略すことも原稿用紙は四百字詰めのものと二百字詰めのものが一般的である。印刷を目的とする原稿ならば二百字詰めでもよいが、普通は四百字詰め(二百字ずつ両面)を使用する。
これまでの縦書きの原稿用紙の書き方を中心に述べてきたが、最近は横書きも多くなってきている。横書きもだいたい縦書きに準じて書くのがよいが、符号の用い方にいくらか違いがある。たとえば、読点をコンマに、句点をピリオドに、引用の場合はかぎかっこを使わずにクォーテーション・マークにしたりすることができる。傍線はアンダーラインとなり、ルビは上につくわけである。かっこも「 」は「 」に、( )は( )にと変わってくる。なお、ローマ字を書き入れる時には、一ますに二字ずつ入れたほうが見やすいようである。
ページは欄外に記入する個所があるのが普通であるが、記入する欄のない場合は右上、左上など統一してしるす。四百字(二百字ずつ両面)の場合は両面にそれぞれページをしるす。
レポートなどの原稿を見ていると、縦書きなのに「12人」「3者」と書いたり、原稿用紙が一枚替わるごとに文の始めでもないのに一字あけたり、横書きの原稿用紙を縦書きに使ったり、何枚もの原稿用紙に段落が一個所もなかったり、思いがけないことがある。
日本での原稿用紙の書き方にはまだ一定していないところもあるが、習慣として決まっている点も多いのであるから、これに従うべきであろう。自分の書くものに愛情を持つならば、全体の調和をとって不統一な形にならないように心がけるべきである。
校正のし方
現代の人々はだれでも年賀状や案内状を始めとして何らかの印刷物を頼む機会を持っているであろう。簡単なものは印刷所にまかせてもよいが、複雑なもの、長文のものは、校正が必要になってくる。この場合に一々ことばで書いていると面倒だし、誤解も生じやすい。やはり基本的な校正の符号を覚えておく必要がある。最初の校正を初校、二番目のものを再校と呼び、以下、三校、四校と呼んでゆく。初校で完全に校正しておいて、以下はその部分が正しくなっているかどうかの確認にとどめるようにすることが望ましい。校正刷りが出るようになってから文章を書き直すことは、多くの障害を生ずるので、努めて避けるべきである。誤植が非常に少なくなり、これならば印刷所にまかせておいてよいという場合は「責任校了」、略して「責了」という。そのまま印刷してよいという場合は「校了」という。校正は赤インキか赤鉛筆で書き入れる。
活字の大きさには、何号というのと何ポイントというのがある。ポイントは「八ポ」のように「ポ」と略す。活字の字体には、明朝体・清朝体・ゴシック体などがある。ローマ字の場合は、スモール−キャピタル・大文字・小文字・ローマン体・イタリック体・ボールド体などがある。このほか、トルアキ(活字を除いてあとをあけておく)、イキ(訂正を取り消す)、オモテ(表けい――)、ウラ(裏けい――)、ゴ(ゴシック体)、アンチ(アンチック体)、イタ(イタリック体)などの略語を使うこともある。
(佐藤喜代治先生 編 『国語表現法』朝倉書店より抜粋)
2 文章
二 文章の実際
1 手紙
2 論説
3 創作
4 レポート・研究論文
この著書から日本語の概論を学ぶ。どのように理論的に構成されているかを学ぶ。
(ダイジェスト版として自分の「ノート」をつくる場合、話すこととは何か、書くこととはどういうことか、どう書くかなど、まとめてノートをつくって国語の理論的側面を整理する)
 ■文化庁『公用文書き表し方の基準(資料集)』(第一法規出版) ■文化庁『公用文書き表し方の基準(資料集)』(第一法規出版)
(国会の速記者研修のテキストと思われる。みなさんも意識して学習してください)
1 内閣告示・内閣訓令
(1) 外来語の表記
(2) 現代仮名遣い
(3) 常用漢字表
(4) 送り仮名の付け方
(5) ローマ字のつづり方
2 公用文に関する諸通知
(1) 公用文における漢字使用等について
(2) 「公用文における漢字使用等について」の具体的な取扱い方針について
(3) 公用文作成の要領(公用文改善の趣旨徹底について)
3 法令に関する諸通知
(1) 法令における漢字使用等について
(2) 法令用語改善の実施要領
4 文部省語例集
(1) 文部省用字用語例
(2) 文部省公用文送り仮名用例集
(3) 文部省文書処理規程の関係条項(抄)
5 その他
(1) 同音の漢字による書きかえ
(2) 「異字同訓」の漢字の用法
(3) 戸籍法及び戸籍法施行規則(抄)
〔付録〕表記に関する諸資料名一覧
 ■ 『公用文書き表し方の基準(資料集)』 ■ 『公用文書き表し方の基準(資料集)』
「文化庁公用文書き表し方」送り仮名用例集以外の使い方
『M&Sディクテ作業基準』(在宅就業でできるトランスクライバーの仕事1990年頃発行)
ア行 言う(明確な発言) 今 明日 行う(×行なう)
いう(伝聞、風聞) イニシャティブ および(×及び)
ハ行 〜ほど(×程) 一人一人 一つ 二つ 図る(×はかる)
(などの一覧表)
■各出版社用字用語基本原則及び作業手順
(毎朝 新聞を読みながら、時事用語等表現法など、用字用語の学習を意識的に取り組んでください)
■『PHP研究所 数字表記基準(A基準、B基準)』
|
|
 |
■『文章の書き方』(成川豊彦著 PHP研究所)
文章作法の学習
|
|
 |
■『インタビュー術』(永江 朗著 講談社)
書籍、雑誌の取材企画がどのように準備されて取材され、その企画構造体を原稿にしている。
本書から筆記理論(インタビュー原稿の構造)を逆に学習していく。
トランスクライバーの筆記に関する理論学習を進める。専用ノートをつくり、トランスクライビングの進め方として背景となる原則をノートし、後輩に教えられるようノートとして自分のためにもまとめる。
そのノートは日本語談話筆記教授法として成長させていく。 |
|
 |
■送り仮名参考、ことばの使い方参考
*『岩波国語辞典』(岩波書店)
*『角川国語辞典』(角川書店)
*『明鏡国語辞典』(大修館書店)ことばの使い方参照
B. 談話筆記の理論的分析──その実践的本質(第6分析)
■ 『ディクテーティング研究』創刊号〜第4号、第6号〜第8号
‘94年版『現代用語の基礎知識』掲載の原稿を加筆、修正しました。
■ディクテの仕事場用語集から;
「会話、対談、講演など話しことばを、雰囲気、ニュアンスを含めて正確に文字・記号、すなわち活字に置き換える」ことをディクテーションという。
日本語で一言で表現することばはない。本などで日常的に話しことばが活字になったものを読んでいるが、これを仕事にするにはたいへん繊細な神経を要求される。
本の編集制作の現場の原点のひとつ。著者はメディアミックス&ソフトノミックス社代表・佐藤正明。
スキャン・ページ(scan pages)
ディクテがひと通り終わったあと、画面で全体的なラキューナの最終チェックのため、テープリスニングすること。意味不明、曖昧でわかりにくい語や用語などの多い場合は、テープ再生速度(ヴォイス再生速度)を実際に話している速度よりも1.3倍程度速くし、流れを把握。前後のコンテキストからことばの類推を図り、口授の同等性(アイデンティファイング)を求める。また、スキャンページ時間の短縮(タイムセービィング timesaving)にもなり、効果的である。
*ディクテ dictationの短縮語としての意味と、仏語のディクテdictee「dikte」 口述、書き取りという意味があります。
ラキューナ(lacuna)
(原稿などの) 脱落、脱文、欠文、空所、空隙
音声言語に対して、「聞き漏らし」「聞き落とし」もラキューナが多いトランスクリプションと表現されることもある。
(理論・知識などの) 盲点、欠点、知識の欠落、凹所
また、トランスクライビィングでノイズ、同時発話、機器音など聞き取れない認識されざる非音声学的音声として表記は〓(ゲタ)で■で表記している。これをラキューナの代用として使っています。
また、欧米においてラキューナは、古文書などの脱語として三点リーダーや六点リーダーなどが使われているようですが、トランスクライビィングのテクニックとして誤記、混乱した一文もラキューナ扱いとしてゲタ(■)をはかせ、■の後ろにカッコ( )で、トランスクライバーが聴いた音声など(音素など)を表記するようにしています。
ガーブルド トランスクリプション(garbled transcription)
都合のよい事実などを勝手に選り抜たり、文章など勝手に改めること。
ステノグラフ(速記)や速記流れのテープ起こしに、その体質が色濃く残っている。
それは仕事の本質から来ている。談話者をディクテーター(dictator;専権を持つ者)として捉えず、ディクテート(dictate;口授して筆記させる)の専権(独裁)性を無視して、談話や証言、独白、講演や対談、インタビューなど、トランスクライバーが勝手に直したり、「です・ます」体に反訳・意訳すること。トランスクライバーの仕事と編集権に基づくライターの仕事との混乱した認識に原因がある。トランスクライバーはライターではありません。まず速記流れの日本語で考えるな、英語で考えろ! 草稿(第一稿)とは何か? が問われる。
マスコミのジャーナリストは正確で忠実なデータ原稿を求めている。錬金術の三流の仕事にトランスクライバーは手を染めてはならない。職業トランスクライバーとしての仕事に徹しよう。それがトランスクライバーが独立した職業人であることの品性である。
二つのディクテーション文型観
ひとつは「話し」ごと性の文型=インタビュー、談話、対談、座談会、テレビ、ラジオ、ビデオ、演劇、映画、その他、日常性としての音声言語、二つはシナリオ(脚本)に基づく、「語り」ごと性の文型=朗読、講演、講義その他、アナウンスとしての音声言語、ディクテートを大別すると、話し(ディスコース discourse)と、語り(リサイト recite)に分けられる。この二つの文型観が成立する。
長谷川慶太郎先生は口頭による談話ふう「語り」といえないか! 「ディクテートの技術」は超一流である。ご講演も整然としている。
ディクテーション(dictation)
談話筆記。談話筆記に協働の生産関係が内在している。
ディクテーター dictator(人間)、dictate(動詞 生産行為)、with transcriber(協働・専門職化)、for transcription (生産物)、という生産関係が成立する。
また、私の現実的な生命活動はトランスクライバーを目指して生産活動の協働の場=企業(エージェンシー・オフィス)と「つながり」を得て、トランスクライビィングができる生産関係が成立する。協働の原型モデルでもある。
トランスクライビィング(transcribing)の生産行為とは、専権を持ったディクテーターに口授され、それを書き取るということ。今日ではインタビューや対談、座談会など、テープレコーダーやICレコーダーで録音し、コンピュータの通信により「音声ファイル」として受け取っている。
この録音声をフォネティックディスコースとして区別し、トランスクライビィングによりトランスクリプション(録音再生原稿)を制作する。
フォネティサイズ(phonet’icize)
音声どおりに表わすこと。弁証法による証明では、日常の現実的側面(正)である「おかあさん」という発話は、理論的側面(反)で オ(o) カ(ka) ア(a) サ(sa) ン(n)の最小単位;音素 phonemeの一音の命(いのち)から成り立ち、このそれぞれ異なった単位の一言をディスコース(discourse)とよぶ。実践的側面(合)であるキーボーディングと画面から「おかあさん」とディクテ(談話筆記・口授の同等性)され、音節は文節に止揚される。
ディクテ・ノート(dicta-note)
ディクテーター(談話者)や出版社の編集者へディクテの「申し送り事項」を伝えるトランスクライバー(録音談話筆記者)の「付記」のこと。談話の録音の中には、ノイズやその他アクシデント、話し手の整理、ラキューナの理由など、編集者の疑問や意思の行き違いがおきないように、原稿の頭や最後に特別な「付記」をつける。それをディクテ・ノートという。
ディスコース(discourse)
談話、talk、speak、tell、say、paroleは、ひとかたまりの音節・文節の意であって、ことばの意味ではない。ディクテーターはディスコースという形式をもってトランスクライバーに伝える。この形式を規定するディスコースには四つの働きがある。
1.発話、語り 2.講演をする 3.草稿する 4.推論する この四つはディクテーションの生産活動を物質的に実現させる。
*ディスコースは口語的で、テキストとは古語的だ。
トランスクライバー(transcriber)
トランスクリプション(録音再生原稿)を制作する人。または、録音談話筆記者。
職業名、専門職化したトランスクライバーは、コンピュータを私的に所有し、ディクテ・マシンのフットコントローラーを足で動かし再生する。プレイ、プレイバックを繰り返して前へ進む。耳はヘッドホンで音声を聴き、両手はキーボーディングして、トランスクライビィングしている。直接、日本語でディクテ(入力)し、ステノグラハー(速記者)のように速記してそれを反訳しない。いまだ速記者が「亡霊」のように徘徊している。
パンクチュエート(punctuate)
句読を入れること。「話し」と「語り」のトランスクリプションに「読みやすさ」を求める息の切れ目、そして論理や意味の切れ目を明らかにする。
句点、「……。」に対して、次に段落改行が働く。
もう一点、「話し」と「語り」のリズム感を出すフォネティック・プロソディー(phonetic prosody)の働き(雰囲気、ニュアンス)を出すこと。
フォネティック・プロソディー(phonetic prosody)
詩(文・一節)、一行の律動、ハーモニー、リズムのことで、ことば(ディスコース)の香り、響き、スタイルや匂いの音感覚が、トランスクライバーの肉体に同化して中身が伝わること。音声言語の音感覚を文字言語へと転換していく。
この場合、ことばのもつアクセント、イントネーション、リズム、ハーモニー、ポーズが音楽的で「ここちよさ」をつくり、快感を上昇させる詩的なるものへの挑戦。
トランスクリプション(transcription)
録音再生原稿、録音談話筆記原稿のこと。この中には出版物の草稿(第一稿)や研修会、セミナーの講演録、会議、ミーティングの議事録、その他があり、いまやステノグラフ(速記)の実体は全くない。速記記号の人力車は博物館の展示物に似ている。
プラクティース・ディクテーティング(practice dictating)
ディクテーティング(トランスクライビィング)の練習。入門の初めはことばを追って書き取っていく。何を言っているのか理解できるが、ことばを追って筆記(入力)できない場合がある。ことばのひとつを次の音節まで広げて書き取っていく。音節は文節になる。
パンクチュエート(句読点をつける)して、段落改行をおこない読みやすさを求めてだんだんと間投詞を略する練習にはいる。
栄久庵憲司氏の話 (『談話の研究と教育?』国立国語研究所 平成元年2月20日)出典 音声言語としての放送
(談話で放送が行われました。その音声記録です)
一寸法師の話はあたしたち小さいときから,アー,よく学校や親たちから聞いている,
エー、大変すばらしいお話です。それは,小さな一寸法師が鬼に向かって挑戦していくお話ですが,エー、鬼がお姫さまをいじめて,で,それを守るために,イ,知恵を働かして,エー,アノ,針の刀を,オー,ひっさげて,エー,鬼の口の中にとびこみ,そして,おなかのなかに入って,エー,鬼を痛めつけると,鬼は降参降参といって逃げて,エー,そのそばにうちでのこづちを残して,エー,一寸法師はうちでのこづちをもって,エー,お姫様と将来,すばらしい生活を,オー,送るというお話です。で,この,オー,お話のよいところ,すばらしいところは,やはり小さいという一寸法師というこの小さな,エー,少年が,エー,大きな鬼に対して戦いを挑んでいくと,エー,この,オー,すばらしいといいますか,エー,勇気の姿と申しますか,そして勝ち得たというところの知恵のよさというか,エー,そういうものが,アー,少年の気持ちを躍々(まま)と,オー,させたんではないだろうとか思うわけです。
談話には句読点や段落改行がありません。句読点を入れて段落改行を行います。
トランスクリプション(文字言語としての録音再生原稿は以下のようにつくります)
一寸法師の話はあたしたち小さいときから、よく学校や親たちから聞いている、大変すばらしいお話です。
それは小さな一寸法師が鬼に向かって挑戦していくお話ですが、鬼がお姫さまをいじめて、それを守るために知恵を働かして針の刀をひっさげて、鬼の口の中にとびこみ、そして、おなかのなかに入って鬼を痛めつけると、鬼は、降参降参といって逃げて、そのそばにうちでのこづちを残して一寸法師はうちでのこづちをもって、お姫様と将来すばらしい生活を送る、というお話です。
で、このお話のよいところ、すばらしいところは、やはり小さいという一寸法師というこの小さな少年が大きな鬼に対して戦いを挑んでいくと、このすばらしいといいますか、勇気の姿と申しますか、そして勝ち得たというところの知恵のよさというか、そういうものが、少年の気持ちを躍々(まま)と、させたんではないだろうとか思うわけです。
ダーシ(──)
二字全角。文の意味内容を明確にさせる。文構造の中でディクテートが中断する。
1.繰り返し強調するとき 2.反復して用語を説明するとき 3.ことばの内容をいったんおわってその内容を説明するとき 4.ディクテートした内容の意味説明 5.ディクテート中、話の内容に流れが一瞬変わって、また本文に戻るとき 6.ディクテート(用語等の)断り、あるいは注意の喚起。
※初心者の中には、−(マイナス)、-(ハイフォン)、ー(音引き)、―(ダーシ)の区別がつかない人もいる。注意して使おう。
六点リーダー(…… 省略記号)
不完全な文の終わりに用いられる。談話していない動詞を入れては正確なディクテーションとはならないので、言わない微妙な表現は「××……。」で処理する。編集者の「ヨミ」にゲタをあずける。また、いわゆる談話の間(間合い・ポーズ)を表わすときも「……。」のように使う。……にはこの二つの使い方がある。
※演劇やドラマの演出などでの「間合い」、しぐさ、セリフ(談話)などの間の「間合い(まあい)」のとり方を……で表わす。
ディクテーティング(dictating)
ディクテートの形式を内容としてみると、口頭による話をoral discourseといい、それを筆記した話はwritten discourseという。後者をdictating(ディクテーティング)と本質規定する。録音テープやICレコーダーによる音声(ヴォイス)・発話をphonetic discourse として区別し、それをトランスクライビィング transcribingと規定する。
トランスクリプションの翻案権
ディクテの仕事場で「ワープロ」における集中が確実に行われていて、その集中にひっぱられるような力と、反対に拮抗する力がはたらく。集中という形で表現の領域へ没入する自分と、それを対象化し批評する自分の精神と肉体とが同時に成立する。ここに、自分の考えや労働が外化【自分の外へ生み出されたモノ(原稿・マティール 物質)】され、協働というかたちでトランスクリプションが「共有」される。
※原稿とはマティール(物質・モノ)である。固有の本質、形式、要素、目的を持つ。
サブジェクト・アイデンティファイング(subject identifying)
ICレコーダーやカセットテープレコーダーで取材された談話が、トランスクリプション(録音再生原稿)の内容と同一物であることを立証する正確なディクテーティングであること。トランスクライバーの専門性とは、訴訟問題やトラブルに注意し、草稿(第一稿)は「証拠」を残すことでもある。口授の同等性(DI)を確保し、ガーブルド・トランスクリプションに陥ってはならない。
ディクーティッド・アイデンティティ(dictated identity)
口授の同等性(DI)、ディクテーターとの共感、生命の歓び、自己実現(神の命令)、社会参加、社会への貢献、トランスクライバー(職業)のトランスクライビィングの歓び。そして、感動の涙。
いろいろな出版社から楽しいお仕事がきます。
ディクテートの対象物としてことばがトランスクライバーに鏡映し、思考の光は屈折反射する。ことばはその瞬間、トランスクライバーの精神と肉体に同化して中身が伝わる。
身体(からだ)いっぱいにことばをころがし、跳ねてなり叫び(共鳴・共感)震え響き合う。そして、泣く。トランスクライバーはことばを置き換え、移し変えてフットペタルを踏み繰り返し進む。録音状態が良好であれば快適である。
プロセス・カット(process cut)
コンピュータの単語登録機能を使い、適時適材に用語を育てキーボーディングを途中省略する。アイデンティティファイングに属した、内側にあるワープロの利用技術(テクノロジー)の開発(ソフトウェア)が求められる。「問題」「アメリカ」「エネルギー」等の名詞に使い、「ございます」「わけです」「そうであるけれども…」などの動詞に使う場合は細心の注意が必要。正確で忠実なトランスクリプションを制作する。取材収録時間が前もってわかれば、仕上がり時間(UP)が分かる。ディクテのタイムセービィングになり、労働生産性を高める。マスコミの出版物というよりも、企業内情報(講演やセミナー、ミーティング)などに多用できる。
トランスクライバーのスタンバイ(stand-by)
座談会などトランスクライバーが会場で取材録音に立ち会って、それをトランスクライブするため発言順をメモする。その立ち会いをスタンバイといい、そのメモをスタンバイ・ノート(standby-notes)という。トランスクライバーは30分前にスタンバイOKし、マイクティスティング等行う。スタンバイ・ノートは発言者のイナンシェーション(enunciation;発言振り等)の特徴も記す。
ビジュアライジング(visualizing)
芸術的具象化。正確なトランスクライビィングをより生かすために芸術的具象化について、人工言語(数字・記号・図柄等)という道具を使い、ディクテで再現しようという試み。コンピュータの機能を引き出し、現場の再現を活字によらないで表現するもの。音楽;#♭♪、場面転換等の表現;□☆#◇、行間を空ける表現(強調、場面の雰囲気、ニュアンス)などをつくり、トランスクリプションを視覚化すること。
トランスクリプションの形式
デイクテート(談話筆記)、対談、鼎談、座談会、インタビュー、セミナー、講演会、ミーティング、聞き取り調査(ヒアリング)などの形式がある。トランスクリプションの形式とは種類である。形式は内容でもある。
C.実践的側面──ディクテ・マシンの操作方法
C.実践的本質(1,2,3で構成)
1.現実的歴史的本質(第7分析)
2.理論的本質(第8分析)
3.実践的本質(第9分析)
モノラルディクテ・マシン(カセットテープ対応)
◆BM-76の生産停止
◆ソニー製 BI-85T
◆M-2020(マイクロカセットテープ用)
新デジタル時代のデジタルディクテ・マシン
(取り扱い説明書の学習、コンピュータ操作の学習、多メディアからの音声の取り込み、変換などの操作技術の学習――カセットテープ音声のデジタル音声ファイルへの変換、MD、CD−RのPCへの音声データの取り込み)
◆小社製作(TSD製) PCフットスイッチ(音声ファイル用)
■ 談話筆記教授法
* 声分けの技術
* 調べものサイト
*
■トランスクライバーのみなさんは高等学校高学年での談話筆記法を教授することを想定して、どのように談話筆記の進め方を教えるか
そうした視座から考えてみましょう。
また録音してPCに音声をデータとして取り込み、トランスクライブ transcribe (録音再生)できるようにしてもよい。
ディクテーション(談話筆記)は、指導原稿を用意し、それを口頭で話して筆記させる。
その指導原稿は、たとえば高校日本史のある一節を切り取り、その部分を口頭で話して筆記させる。歴史専門用語、固有名詞(歴史上の人物名など)、史実表記に混乱はないか。
また、たとえば高等学校『現代政治・経済』の一節〜
(高等学校『現代政治・経済』清水書院より)
*「フリーター」を考える―きびしい雇用状況と不安定雇用―
(記者やライターさんの取材メモというべき、出てくることばと用語を時系列的にメモして流す。
高校生のレベルで漢字、仮名混じり文で筆記されているかどうかも評価対象となる)
◆雇用状況 不安定雇用 雇用形態の多様化 派遣社員 非正規社員 自由な労働時間選択 特定の技能 リストラ 低コストで雇用調整 安全失業率 長期不況 中高年層の大規模なリストラ 就職難 賃金の安い生産部門を移転 終身雇用 年功序列型賃金制 卸売 小売業 雇用保険 雇用契約 派遣元事業所 指揮命令 労働条件 就労 やりたいことがみつからない モラトリアム型 夢追求
プロの職業トランスクライバーのノウハウになるが、電子録音物(媒体=月刊誌)は中身が見えないので、中身をチェックする前に5分間再生して「流し聴き」し、内容が分かり録音状態なども前もってわかると、ディクテにかかる時間がわかる。
トランスクライバーはどんな仕事をしているのか
マスコミの取材(インタビュー)で談話は「誰に向かって、何のために、何を、どのようなことばを使って、どんなふうに話すか」(佐藤喜代治先生)取材が行なわれている。
高校生になると、進路選択が行なわれ、文系と理系に分かれる。
本局でのトランスクライバーのキャスティングでは適材適所で担当者が選ばれる。
「著者はどんな先生(フルネーム)で、媒体(月刊誌・内容の難しさ)はなんで、何を、テーマはなんで、どのようなことば(用語、専門用語)を使って、どういう方法(取材レジュメ、質問の内容、対談の相手の先生は)で、お話しされているか」本局では編集者からお仕事のお電話をいただくとき、こうしたことを伺ってキャスティング決定の参考にしている。
以上、こうした立場で高校生にも支援しなければならないだろう。
それは、どんな「仕事」か、学習の内容を前もって知らせることが必要である。何をするのかが前もって分かる。
こうすれば高校生は精度の高い談話筆記原稿を仕上げるだろう。
録音再生(トランスクライブ)を利用する場合、高校生のトランスクライバーには、録音の終わりに「ディクテはここまでです。しっかりできましたか? 大変でしたでしょう。ごくろうさま」と言って、生徒とのコミュニケーションも忘れずに。初心者のトランスクライビングは録音時間60分に対して、14時間〜16時間かかるのが普通だ。
トランスクライバーは、「ディクテ・ノート」でディクテ後記を記し、先生への一言コミュニケーションを忘れずに。
[ハード志向感覚の日本人は、もう少し欧米人のように気楽に録音を身近にして楽しもう]
*「飛び出せ中小企業!!」―産業構造の変化と中小企業―
◆産業構造 清田製作所 コンタクトプローブ(接触型深針)という製品 半導体集積回路 独創的な技術・サービス ベンチャー企業 地場産業 下請け 日本経済の基礎を形成 労働条件の格差 市場での競争力 半導体メーカー 端子間の間隔が細かくなる 従来より細い針がつくられるかどうかが製品開発の鍵を握っている プレス工場 ハーモニカ(雑貨) カメラの露出計 レコード針(精密機器) 半導体検査針(電子機器) 製造業 中小企業は自らの力で 新規開業 企業が減少 中小企業を取り巻く環境変化 促進 成長性
* どのようなことばや用語で教科書のテーマが綴られているか、そのことばが正しく筆記されるか、そこを国語の時間に、このような指導原稿を口で言って書き取らせる。
* 国語教科では繊細な表現を聞き取って、聞き漏らしのないように、漢字や仮名混じり文をつくらせる。口頭の話には句読点がないが、息の切れ目や意味の切れ目に句読点を入れる練習をさせて、段落改行も教える。
* 高校生が、人生をどう生きていくかを考える学習など、よく学ぶには、たとえば「現代創作修身」として、「目標と努力について」、口頭で言って正しく筆記できたかどうかをみる。教師は、生徒に口で言って書き取らせることが教育につながるし、教育効果が分かる。ディクテーションは、生徒自身が教師の談話を対象化して筆記する。それが教育につながる。教師は生徒のこころに響くことばを磨く。生徒はこころにないことばを見抜く。
* 国語では長く断片的に切り取り「読み、書き」ソロバンの教育を行なってきたが、コンテンツ(コンテキスト)を通して談話筆記させる(ディクテーション;文章づくりを通して)で、漢字や表現法を学ぶ。特に権威主義的なつめ込み教育や暗記教育から決別し、教育理念なども入れて談話筆記させる。筆記させて考える力をつける(ディクテーション教授法の真髄である)
* 作家の小説、批評文など談話筆記させる。日本語の繊細で豊かな表現を学ぶ。
* わからないことばや用語などの表記法・表現法については、インターネットで調べさせる。その調べる方法を教授する。
* 生徒は何が筆記できないで、どこのどんな談話に混乱をした表記をし、筆記に間違いがあるかなど、そこが浮き彫りになる。プロの世界では品質の悪い原稿と言われる。書き取れていなく、理解されていない。知らないことばは聞き取れない。日本語かカタカナ語の聞き分け(区別)が出来ず、何を言っているのか、筆記できない。
* 生徒の学力を測定するには、正しく筆記するために背景となる理解力をもっているかどうかが分かる。高校生がつくった談話筆記原稿のレベルを評価することができる。
(省略)
■このような枠組みから談話筆記教授法の構想を進める。
ディクテーション dictation や ディクテート dictateの本質は、口授――口頭で授ける、という意味である。内在的に口授の教育指導文化をもっている。
家庭で子どもの親の同化模倣も口頭(話しことば)によって伝えられる。
「速記流れのテープ起こし」は無思想的で無原則的である。「テープ起こし術」を宣伝した。ここに違いがある。
ディクテーション教授法は指導的立場から口頭で授けるという意味だ。ここには、ののしり合いの口論や係争ごとは、ディクテートの原義においても、口頭によって授けるとは思想的になじまない。ぼくたちは普段の市民生活の中にいる。
ある人は、速記とぼくたちの仕事に違いを見ようとは思わなかっただろう。テープ起こしと名前だけが違う別の名だと思い込んでいた人もいた。
ディクテートと「速記流れのテープ起こし」とは本質的に立場が違う。係争やののしり合い、口論などの論理文化を受け入れるには難しい思想的立場がある。
ぼくたちはマスコミ社会で生きてきた。共感と自己実現を求めて良質なコンテンツの創造に関わってきた。
また、こうした立脚点を悪意に利用されることはお断りである。
今、あまり多くを主張する気はない。
「速記流れのテープ起こし」と「ディクテーション教授法」には思想的衝突がある。それは、アジアとヨーロッパの歴史(文明)との衝突なのだろうか。
もう一点、口授の教育指導文化の思想的真髄が、口頭で授けるという談話の意味として、禅の不立文字の談話であってもテキストと対面する。このトランスクリプション(録音再生原稿)は、その仲立ちをするだろう。耳からことばとことばの行間から見えてくる。ぼくたちは未来の大きな可能性の中に生きている。
いまモノづくりの技能は次代への伝承という課題をもっているが、談話と筆記の一致が生み出す可能性を、ぼくたちはここにミッション(使命)を見出している。
(平成18年6月20日「営業情報」に投稿された本稿を加筆修正しました)
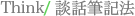
|